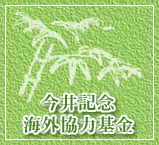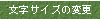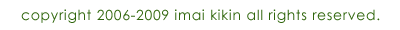ジュマの内部抗争による被害児童教育支援
対象地域
バングラデシュ: チッタゴン管区ランガマティ県
背景
バングラディシュは、ベンガル人(インド・アーリア系)イスラム教徒が大多数を占める国であるが、事業対象地のチッタゴン丘陵地帯には「ジュマ」と呼ばれる複数のモンゴロイド系少数民族(厳密には11〜13の少数民族の総称)が集住している。ジュマとバングラデシュ政府の間では、1973年から約20年にわたって紛争が行われてきた。1997年に和平協定が結ばれて公には紛争が集結したとされるものの、和平協定の内容の不履行や、軍の駐屯がその他地域と比べて集中していることなどから、少数民族が抑圧される状況が生まれており、軍による一方的な土地収奪、紛争時に行われた多数派民族の入植政策による軋轢や襲撃事件が長く問題視されてきた。さらに近年では、ジュマの政治グループの分派および内部抗争が深刻化している。各政治グループは武器を手に取り、暴力によって住民から金銭の徴収などもおこなっており、ある報告によれば、これまで内部抗争によって600人以上のジュマが殺害されている。現在では、内部抗争によってジュマ社会全体の弱体化が進むと同時に、当地での平和へのはたらきかけも困難を深めている。
多数派ベンガル人との共存や軍との対話などの本質的な平和へのアプローチのためには、まず内部抗争の解消が先決だ。しかし利害が相反する政治グループがせめぎ合う中での直接的な行動にはリスクが伴うため、本事業では支援の第一歩として、内部抗争によって被害に遭った児童・生徒の奨学金支援活動を行う。実施団体はこれまでも紛争被害児童への奨学金支援の経験がある(現在も12人への支援を実施)が、本事業ではとりわけ内部抗争による被害にフォーカスした取り組みとして、既存の紛争被害児童支援の大幅なアップグレードを新たに行う。また、本人や家族の承諾のもと、彼ら彼女らの具体的なライフヒストリーや事件に関することも日本で発信することで、当地域で起きている抑圧構造や民族対立の課題を国際社会に周知する。
事業目的
本事業は、内部抗争被害者の救済と、若者の過激化予防を目的とする。
内部抗争の被害のケースとしては、親が敵対グループによって殺害されるケースが多く、経済的・社会的な選択肢が限定される。そのため、学校に通うための経済的なハードルをジュマ・ネットが支援することで、彼ら彼女らが教育を享受することができ、社会的な選択肢を与えることができる。さらに、そうした児童たちが教育を通して社会的な選択肢を手に入れることは、彼らが政治グループへと加入していくことを予防する働きにもつながる。
事業内容
1. 被害児童への奨学金支援(既存3人、新規5人の計8人。年齢層は約5〜18歳)
2. 被害児童へのキャリア教育(日本語教育や環境教育を予定)
3. 家族の自立支援(生活状況や家族の希望を踏まえて実施の有無を検討)
4. 内部抗争の被害児童・家族の実態把握と日本での情報発信(600部)